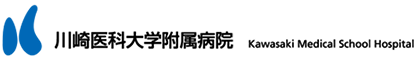リハビリテーションセンター
更新:2025年4月1日
理学療法部門
業務概要
理学療法(PT)は、病気・けが・障害・高齢や手術により身体が不自由となった患者さんに対して、運動機能の維持と改善を目的に、運動および温熱・電気などの物理的手段を用いて行われる治療法です。
実際には、個々の患者さんの身体機能面・心理面・リスク管理を考慮し、適切な目標と治療プログラムを設定したのち、日常生活活動(ADL)の改善を図り、最終的にはQOL(生活の質)の向上を目指します。
基本的な治療内容は以下のとおりです。
1.運動療法
筋力・関節可動域・バランス能力・痛みの改善(回復)などを通じて、基本動作(起きる・座る・立つ・歩く)などに対する運動療法を行います。その際には、必要に応じて義肢装具や補助具を使用します。
当院では、リハビリにロボットを導入し正確な動作補助や訓練の難易度を調整しながら個人に合った負荷量設定し、ロボット特性を生かしたリハビリを提供していますトヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、脳卒中などによる下肢麻痺のリハビリテーション支援を目的としたロボット「ウェルウォーク」と「ロボットスーツHAL®(Hybrid Assistive Lumb®)」を導入しています。

ロボットスーツHAL®(Hybrid Assistive Lumb®)医療用下肢タイプを用いたリハビリテーションを入院・外来で2023年10月より開始しています。HAL®医療用下肢タイプは、脳・神経・筋系の機能低下で身体を思うように動かせなくなった方の歩行能力の改善を行う治療です。 人が体を動かそうとしたときに体表に出る「生体電位信号」を皮膚に貼ったセンサーで検出し、装着者の意思に従った動作を実現します。神経・筋疾患などで身体が動かしづらくなってしまった方であっても、脳からの信号にもとづいたこのような運動を繰り返し行うことができるため、脳神経機能が強化され、歩行能力の改善効果が期待されます。また運動量が増え、生活の質(QOL)の改善につながります。

2.心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは、早期の退院や社会復帰を促し、退院後の再発防止までを含めた幅広い目的を持って多職種で行われるプログラムです。その中でも、主軸となる運動療法は、個々の患者さんに適した運動プログラムを立案し、体力向上・症状の軽減・生活の質(QOL)の向上を目指します。
 心疾患リハビリテーション室
心疾患リハビリテーション室
エルゴメーターや筋力トレーニング機器を使用して、心臓リハビリテーションを実施しています。複数の心電図モニター同時に管理しながら集団でのリハビリテーションが可能です。
【使用機器】
エルゴメーター(リカンベント、アップライト)、筋力トレーニングマシン、セラバンド等
 心肺運動負荷試験(CPX)
心肺運動負荷試験(CPX)
医師同席のもと、運動耐容能や心機能の評価のために心肺運動負荷試験を実施しています。リハビリテーションの効果判定だけでなく、最適な運動負荷量の設定が可能です。
【使用機器】呼気ガス分析装置、エルゴメーター、12誘導心電図モニター
3.呼吸リハビリテーション
呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患・間質性肺炎・肺炎・誤嚥性肺炎など)の患者さんに対して、呼吸の改善(呼吸効率の改善、息切れの軽減)、運動能力の改善(活動の低下を予防)、体力の向上、日常生活の自立や生活の質(QOL)の向上を目標に行います。
 MI-E(排痰補助装置)
MI-E(排痰補助装置)
呼吸リハビリテーションにおいて機器を用いた排痰補助を実施しています。神経筋疾患や脊椎損傷などで呼吸機能が低下した患者さんに対して効果的です。
4.物理療法
痛みの改善を目的に、温熱療法・水治療法を行っています。麻痺や萎縮した筋肉に対して、電気刺激療法(G-TES、IVESなど使用)を行い筋力の維持・回復を図ります。
 電気刺激療法(G-TES)
電気刺激療法(G-TES)
5.車椅子・補装具の調整
6.ご家族への介助方法の指導
7.家屋改造・介護用品の助言や指導
理学療法の対象疾患
当院の理学療法部門の対象疾患です。乳幼児から高齢の方まで、対象疾患も多岐にわたっています。
- 脳血管障害、その他の脳疾患(頭部外傷、脳炎など)
- 脊髄損傷、その他の脊髄疾患(二分脊椎など)
- 発達障害、その他の小児疾患(脳性麻痺など)
- 神経および筋疾患(筋ジストロフィー、多発性硬化症、パーキンソン病など)
- 変形性関節症、関節リウマチ、その他の骨・関節疾患(外傷を含む)
- 呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)
- 循環器疾患(心筋梗塞など)
- 代謝疾患(糖尿病など)
- 悪性腫瘍の治療中・治療後
- 開腹・開胸手術の術後
- 熱傷
- リンパ浮腫
特徴・特色
現在、理学療法⼠が3つのチームに分かれて、集中治療室や一般病棟、特定機能病院リハビリテーション病棟に専門スタッフを配置しています。外来診療では、リンパ浮腫外来や⼩児外来など⾏っています。日々、患者さんに満足していただけるリハビリテーションサービスができるよう努めています。
実習生の受入れと教育
理学療法部門が教育施設として関わっているのは、以下の分野です。
長期実習学生の受け入れ
川崎医療福祉大学、川崎リハビリテーション学院の2校から、臨床実習生を受け入れています。臨床実習担当者を中心として、多くの病院職員が関わって学生指導を行います。
当センターで臨床実習を指導する上で留意していることは、医療現場で必要な接遇と、評価と問題点抽出・目標設定・治療⽅針について整合性のある治療推論のもと急性期から回復期での必要な理学療法を提供できるように指導が行われています。
急性期からのベッドサイド訓練・回復期病棟での病棟練習・小児外来・装具回診など、見学の機会を多く持てるように配慮しています。
他部門の実習生教育へのコ・メディカルとしての関わり
医学部、看護学科をはじめ多くの分野の実習生が臨床実習を行う教育施設であることから、臨床場面を通じて多職種で学生指導に関わります。
専門学校非常勤講師
隣接する川崎リハビリテーション学院の非常勤講師として毎年数名が委嘱されており、専門科目を担当しています。
他施設・一般の見学および研修の受け入れ
希望により適宜対応可能です。