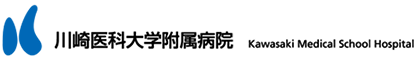特徴・特色
勝村元学⻑(血管)、藤原名誉教授(⼼臓)が 外科治療のパイオニアとしてはじめ、三代⽬種本名誉教授に より⼤きく発展した50年の歴史を持つ教室です。冠動脈バイパス術や下肢動脈バイパス術などを全国に先駆けて導⼊してきました。わたしたちは、患者さんやご家族と長く向き合ってきた結果、患者さんの人生を今後ずっと支えていける治療を心がけるようにしています。そのために過去の膨大なデータ解析や報告から、メリットが無い無駄な治療や早すぎるタイミングでの治療は勧めないように気をつけて、よりよい手術方法や時期を提示させていただきます。
心臓弁膜症についてはできるだけ人工弁の使用を避けて、自己弁を温存した弁形成術を積極的に行って良好な成績を出しています。また、大動脈弁のカテーテル人工弁植込術(TAVI)や低侵襲心臓手術(MICS)も行っており各患者さんに最適な治療を選択するように努力します。冠動脈は心拍動下、心停止下に加えてMICSの3つの術式から最適治療を選択します。大動脈瘤や血管治療についてはカテーテルによるステントグラフト治療も早期から導入し、難度の高い枝付きステントグラフトなど低侵襲治療の提供も可能です。
下肢静脈瘤をはじめとした静脈疾患は生命予後に影響することは少ないですが、患者さんのQOLには多大な影響を与える疾患であり無視することはできません。この分野でも内視鏡手術、レーザー治療などの最新治療を積極的に行っています。
これら各分野を専門性の高い医師が担当します。すべての分野で、手術後の再手術や難易度により他院で治療を断られた患者さんもできるだけ受け入れて治療を検討しています。そのような患者さんもご連絡ご相談ください。

診療部長・責任者
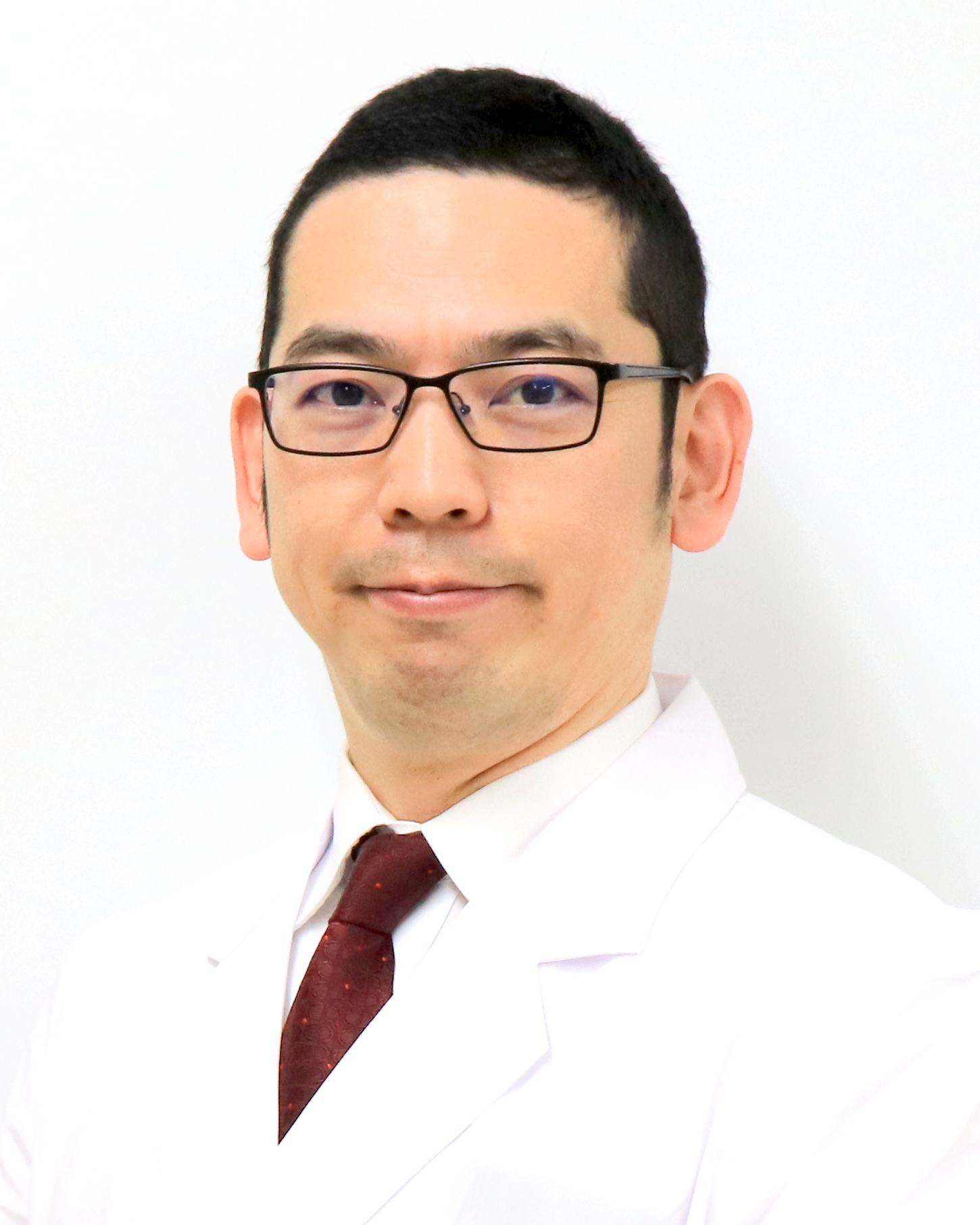

- 部長(教授) 畝 大 Dai Une
認定医・専門医・指導医 日本外科学会外科専門医・認定医、心臓血管外科専門医・修練指導者、胸部ステントグラフト実施医
- 出身大学
- 岡山大学 H13.3 卒業
主な対象疾患
関係する症状
心臓、大動脈、血管(動脈、静脈)と全身の幅広い範囲に関わりますので症状はさまざまです。下記症状があればかかりつけ医や当院にお気軽に御相談ください。
心臓病では、胸が痛くなる、ドキドキするという症状が出ることがあります。歩行時や階段での息切れの悪化は年齢のせいにしがちですが心臓病が原因のこともあります。これらは治療後に速やかに楽になることがたくさんあります。
大動脈では、お腹を押さえるとドクドクと拍動しているものや、急激な胸痛/腹痛が症状になります。多くは無症状ですので健康診断や他の科の検査で偶然みつかります。
動脈や静脈の病気も治療しています。歩くと足が痛くなり、休むと痛みがなくなる。あるいは足が冷たい。そのような時は、動脈の病気です。よく整形外科の病気と間違われます。また足が腫れるなどの症状があると静脈瘤の可能性もあります。そのような診断を無侵襲的に行い、治療していますので、気軽に受診してください。
- 下肢症状に関しては、しばらく歩くと足が張ってくる、痛む、足が痺れる、冷えるなどの症状
- 動脈の病気が疑われます。よく整形外科の病気とまちがわれます。
- 安静時にも足が痛む、あるいは潰瘍を作っている
- 急いで受診される必要があります。
- 足が腫れる、また静脈の瘤(こぶ)が飛び出しているといった症状
- 静脈の病気の可能性もあります。そのような疾患診断を無侵襲的(痛くない)に行い、治療していますので、お気軽に受診してください。
治療している主な病気
臨床領域としては、心臓、血管の外科治療を担当させていただいておりますが、とくに救急疾患に対しては迅速な対応を行います。緊急時にはヘリコプター搬送や救急車搬送で患者さんの受け入れを行っております。
- 心臓
- 後天性弁膜症(大動脈弁、僧帽弁)、狭心症、心筋梗塞、心不全、不整脈の外科治療
- 血管(静脈)
- 下肢静脈瘤、深部静脈血栓症、血栓性静脈炎、静脈うっ滞性潰瘍の診断・治療
- 血管(動脈)
- 大動脈瘤(胸部、胸腹部、腹部)、解離性大動脈瘤の外科的治療、閉塞性動脈硬化症、閉塞性血栓血管炎(バージャー病)、レイノー氏病、血管外傷の治療
専門診療・専門外来
実績
2024年1~12月
| 心臓胸部大動脈手術(オフポンプ冠動脈バイパス術と人工心肺使用症例) | 105 |
| 弁膜症手術(複合手術含む) | 50 |
| 冠動脈手術(複合手術含む) | 40 |
| 胸部大動脈手術(複合手術含む) | 16 |
| その他(心内血栓など) | 6 |
| 上記のうちMICS(低侵襲アプローチ) | 11 |
| TAVI (経カテーテル的大動脈弁置換術) | 24 |
| ステントグラフト内挿術 | 96 |
| 胸部大動脈 | 42 |
| 腹部大動脈 | 54 |
| 腹部大動脈手術(開腹) | 9 |
| 末梢血管手術 | |
| 静脈瘤 | 98 |
| 透析用動静脈シャント | 76 |
| 下腿動脈バイパス術 | 9 |
| 動脈疾患へのカテーテル治療 | 81 |
2023年度
| 患者数(延べ) | 外来患者数 | 5,188人 |
|---|---|---|
| 入院患者数 | 8,527人 |