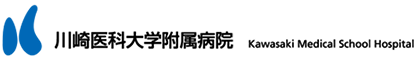高次脳機能障害とは
更新日:2024/10/10
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、脳血管障害(脳卒中)や脳外傷の影響で生じる、*失語症・*注意障害・*記憶障害・*遂行機能障害・*社会的行動障害などの総称です。ほかに *失行・*失認なども代表的な高次脳機能障害の一部です。このように高次脳機能障害とは、脳の何らかの損傷(機能不全)によって生じる、認知機能(知能)あるいは非認知機能(情動)障害の総称といいかえることができます。 (* の具体的症状については下記チェックリストをご参照ください。 )

「高次脳機能障害」という用語は、本邦においては主にふたつの用法があります。ひとつは先に述べたような、脳の機能異常によって生じる認知/非認知機能障害のすべてを含む広義(広い意味)の高次脳機能障害です。このなかには、アルツハイマー型認知症や先天性の知的障害などによるものも含まれます。もっと極端な話をすれば、意識障害によって認知(非認知)機能が働かないような場合まで含まれます。もうひとつは、狭義(狭い意味)の高次脳機能障害です。これは日本国内限定の行政診断的用法で、先の広義の高次脳機能障害のなかで、以下のような条件を満たした場合のみに使用されます。その主な条件とは、①脳卒中や脳外傷などの非先天性/非進行性疾患等によって脳に傷があることがC T や MR I などの画像で確認できる、②日常生活または社会生活の制約の原因が、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・社会的行動障害などであるとなっています。つまり進行性の変性疾患であるアルツハイマー型認知症や、先天性疾患である発達障害などによる高次脳機能障害は含まれません。また交通事故等による外傷で、MR I や C T など の画像で脳に明らかな傷が確認できない場合も含まれません。

このように本邦においては、 「高次脳機能障害」という用語に、広義/狭義のふたつの意味が含まれることで、高次脳機能障害の診断/理解は難しいといわれています。当院は、岡山県高次脳機能障害支援拠点病院に指定されており、大学病院ならではの、高度人材・最新機器・情報ネットワークを組み合わせて、診断から社会参加支援まで個々の患者さんのニーズに寄り添ったきめ細やかで幅広い高次脳機能障害診療を行っています。当科では高次脳機能障害をはじめ様々な障害に対し、リハビリテーション(病気の治療のみならず心理的支援/生活就労支援まで行う全人的医療)および当院の理念に沿った診療を心がけております。次のチェックリストをみて気になった方は主治医の先生に相談してみてください。


「高次脳機能障害」という用語は、本邦においては主にふたつの用法があります。ひとつは先に述べたような、脳の機能異常によって生じる認知/非認知機能障害のすべてを含む広義(広い意味)の高次脳機能障害です。このなかには、アルツハイマー型認知症や先天性の知的障害などによるものも含まれます。もっと極端な話をすれば、意識障害によって認知(非認知)機能が働かないような場合まで含まれます。もうひとつは、狭義(狭い意味)の高次脳機能障害です。これは日本国内限定の行政診断的用法で、先の広義の高次脳機能障害のなかで、以下のような条件を満たした場合のみに使用されます。その主な条件とは、①脳卒中や脳外傷などの非先天性/非進行性疾患等によって脳に傷があることがC T や MR I などの画像で確認できる、②日常生活または社会生活の制約の原因が、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・社会的行動障害などであるとなっています。つまり進行性の変性疾患であるアルツハイマー型認知症や、先天性疾患である発達障害などによる高次脳機能障害は含まれません。また交通事故等による外傷で、MR I や C T など の画像で脳に明らかな傷が確認できない場合も含まれません。

このように本邦においては、 「高次脳機能障害」という用語に、広義/狭義のふたつの意味が含まれることで、高次脳機能障害の診断/理解は難しいといわれています。当院は、岡山県高次脳機能障害支援拠点病院に指定されており、大学病院ならではの、高度人材・最新機器・情報ネットワークを組み合わせて、診断から社会参加支援まで個々の患者さんのニーズに寄り添ったきめ細やかで幅広い高次脳機能障害診療を行っています。当科では高次脳機能障害をはじめ様々な障害に対し、リハビリテーション(病気の治療のみならず心理的支援/生活就労支援まで行う全人的医療)および当院の理念に沿った診療を心がけております。次のチェックリストをみて気になった方は主治医の先生に相談してみてください。

執筆者

-
部長(教授)
平岡 崇
Takashi Hiraoka
専門分野
高次脳機能障害、嚥下障害、小児発達障害
認定医・専門医・指導医
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・認定臨床医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本臨床倫理学会臨床倫理認定士、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、日本医師会認定産業医
- 出身大学
- 川崎医科大学 H8.3 卒業

- 部長(教授) 平岡 崇 Takashi Hiraoka
専門分野
高次脳機能障害、嚥下障害、小児発達障害
認定医・専門医・指導医
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・認定臨床医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本臨床倫理学会臨床倫理認定士、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、日本医師会認定産業医
- 出身大学
- 川崎医科大学 H8.3 卒業