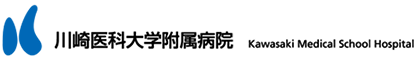慢性腎臓病(CKD)の進行を予防する
慢性腎臓病(CKD)の進行を予防する
自分の腎臓病を知ろう!
慢性腎臓病(CKD)の診療で重要なこと、①現在の腎機能、②治療の目標について確認しましょう。①に関してはeGFRを見ることでわかります。eGFRの値によってCKDの重症度が分かれます。もう一つ重要な指標が蛋白尿です。これにより現在のご自身の重症度を見ることができます。まずは自分の腎臓を知るところから始めましょう。そのためには是非ともかかりつけ医と相談して状態を知りましょう。
腎臓を守ろう!
腎臓は先ほどお話ししたとおり、身体の負担を一身に受けて働いてくれています。腎臓を守るためには腎臓の負担をとってあげる必要があります。少しでも楽をしてもらいましょう。具体的には体重の制限、減塩、水分摂取のポイントを押さえておきましょう。体重が重い、体格が大きいということは、腎臓が捨てるべきゴミが多くなる訳です。そのため腎臓にとっては負担が増えることになります。塩分も同様です。塩分摂取が増えると、血圧が上がる要因になります。高血圧は腎臓にとって最も影響がある因子です。また塩分摂取が増えると蛋白尿が増えてきます。蛋白尿は腎臓が出す悲鳴ですから、少しでも減らした方が腎臓は長持ちします。塩分摂取の目標値は6g ⁄ 日となっています。以前に比べて食事の欧米化により日本人の平均塩分摂取量が減ってきています。それでも男性10・9g ⁄ 日、女性9・3g ⁄ 日となっています(2019年時点) 。このため6gを達成するのは色々と工夫が必要となります。近年は減塩食材も増えているので、活用して腎臓の負担をとってあげましょう。また、飲水も重要です。一般的に1・2L 程度の尿量を作ると腎臓は尿を濃くしたり薄くしたりすることなく、必要な量のごみを排泄することができます。不感蒸泄(皮膚や呼吸から蒸発する水)の量が500mL‒700mLくらいとされています。食事から入る水分がちょうどその程度となります。このため食事以外で1・2Lの水を飲むことで腎臓が負担なく尿を作ることができる訳です。こまめに飲むことが重要です。また腎機能の程度によってするべき生活習慣は変わってきます。このため当院では多職種(栄養士、薬剤師、理学療養士など)で患者さん個別の対応を行なっています。

CKDの治療薬
近年、CKDの治療も様変わりしてきました。従来は降圧薬であるアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)などが使用されていました。新たに、糖尿病の治療薬であったSGLT2阻害薬がCKDの治療薬として承認されています。また糖尿病合併のCKDでは新規ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬が承認されており、以前に比べて選択肢が増えてきています。どの薬剤も腎臓の負担をとり、蛋白尿を減らすことで腎臓を守る作用があります。今後さらに新たな治療薬が出る可能性も高いです。一方でこれらの薬剤は腎機能を改善する治療薬ではないため、早期に診断して早期に治療を始めることが重要となります。現在は人生100年時代となっており、100歳まで腎臓をもたすことは容易ではありません。CKDは症状なく進行する病気です。このため健康診断やかかりつけ医と定期的な血液検査や尿検査をすることで早期発見し必要な対応を行いましょう。

執筆者

-
副部長(准教授)
長洲 一
Hajime Nagasu
専門分野
腎臓病、高血圧、血液浄化療法
認定医・専門医・指導医
日本内科学会認定内科医、日本高血圧学会高血圧専門医・指導医 日本腎臓学会腎臓専門医、多発性嚢胞腎協会PKD認定医
- 出身大学
- 川崎医科大学 H15.3 卒業

- 副部長(准教授) 長洲 一 Hajime Nagasu
専門分野
腎臓病、高血圧、血液浄化療法
認定医・専門医・指導医 日本内科学会認定内科医、日本高血圧学会高血圧専門医・指導医 日本腎臓学会腎臓専門医、多発性嚢胞腎協会PKD認定医
- 出身大学
- 川崎医科大学 H15.3 卒業