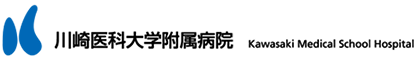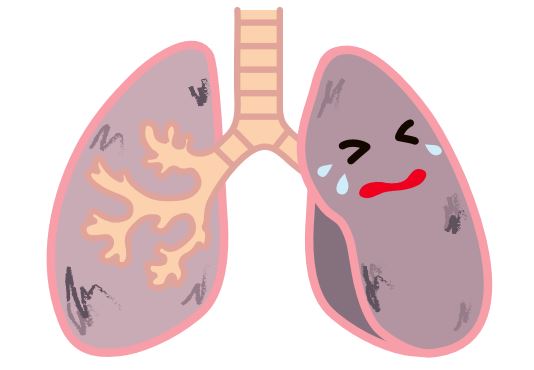肺がんの治療と予防について
肺がんの治療
肺がんの治療は3つの柱(手術療法・薬物療法・放射線療法)からなります。
「患者さんひとりひとりに合わせた治療」と「身体に負担をかけない治療」が現在の肺がん治療の原則です。
切除可能な肺がんに対しては手術がまず選択されます。肺がんの組織型や進行度、また患者さんの体力などを総合的に検討し切除範囲を決定します。基本は、がんが存在する肺葉と所属するリンパ節を切除する「肺葉切除およびリンパ節郭清」で、 これが「標準手術」と呼ばれます。早期の肺がんや、 体力的に「標準手術」が難しい患者さんには切除範囲を小さくした「縮小手術」も選択されます。
近年の手術の最大の進歩としては「低侵襲手術」が挙げられます。胸腔鏡(内視鏡)を用いて数センチメートルの傷を2、3か所おいて行う「胸腔鏡手術」の進歩により、患者さんへ与える身体的負担が減り、早期の退院・社会復帰ができるようになりました。
当院でも早くから胸腔鏡手術を取り入れてきた歴史があり、最近では1つの傷のみで手術を行う「単孔式手術」を導入して患者さんへの負担を極力減らす手術を行っています。

切除ができない肺がんには薬物療法や放射線療法が行われます。胸の中のリンパ節に転移がある場合には薬物と放射線の併用療法が、 遠隔転移 (ほかの内臓への転移)のある肺がんには主に薬物療法が行われます。薬物療法には「抗がん剤治療」 「分子標的療法」「免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬) 」があり、新しい薬も次々と開発されています。
現在では、患者さんから採取したがん組織を用いて、薬の効果を予測する「EGFR」や「PD-L1」などのマーカーを測定し、個々の患者さんに最適な薬剤を選択して治療を行う「個別化治療」が標準となっています。従来の治療と比較して、個別化治療では治療効果を向上させ副作用を軽減させることが可能になってきました。
また、薬物療法や放射線療法の進歩により、初めは切除困難であった肺がんが切除可能になるケースも増加しています。このように内科・外科・放射線科が一体となって治療を行う「集学的治療」によって肺がんの生存率は向上しています。

「患者さんひとりひとりに合わせた治療」と「身体に負担をかけない治療」が現在の肺がん治療の原則です。
1.手術療法
切除可能な肺がんに対しては手術がまず選択されます。肺がんの組織型や進行度、また患者さんの体力などを総合的に検討し切除範囲を決定します。基本は、がんが存在する肺葉と所属するリンパ節を切除する「肺葉切除およびリンパ節郭清」で、 これが「標準手術」と呼ばれます。早期の肺がんや、 体力的に「標準手術」が難しい患者さんには切除範囲を小さくした「縮小手術」も選択されます。
近年の手術の最大の進歩としては「低侵襲手術」が挙げられます。胸腔鏡(内視鏡)を用いて数センチメートルの傷を2、3か所おいて行う「胸腔鏡手術」の進歩により、患者さんへ与える身体的負担が減り、早期の退院・社会復帰ができるようになりました。
当院でも早くから胸腔鏡手術を取り入れてきた歴史があり、最近では1つの傷のみで手術を行う「単孔式手術」を導入して患者さんへの負担を極力減らす手術を行っています。

2.薬物療法・放射線療法
切除ができない肺がんには薬物療法や放射線療法が行われます。胸の中のリンパ節に転移がある場合には薬物と放射線の併用療法が、 遠隔転移 (ほかの内臓への転移)のある肺がんには主に薬物療法が行われます。薬物療法には「抗がん剤治療」 「分子標的療法」「免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬) 」があり、新しい薬も次々と開発されています。
現在では、患者さんから採取したがん組織を用いて、薬の効果を予測する「EGFR」や「PD-L1」などのマーカーを測定し、個々の患者さんに最適な薬剤を選択して治療を行う「個別化治療」が標準となっています。従来の治療と比較して、個別化治療では治療効果を向上させ副作用を軽減させることが可能になってきました。
また、薬物療法や放射線療法の進歩により、初めは切除困難であった肺がんが切除可能になるケースも増加しています。このように内科・外科・放射線科が一体となって治療を行う「集学的治療」によって肺がんの生存率は向上しています。

肺がんの予防
肺がんの最も有効な予防法は禁煙です。国立がんセンターの研究では、喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4・4倍、女性では2・8倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く喫煙量が多いほどそのリスクが高くなる、とされています。また、受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんのリスクを2〜3割程度高めます。禁煙を始めるのに遅すぎることはありません。


執筆者
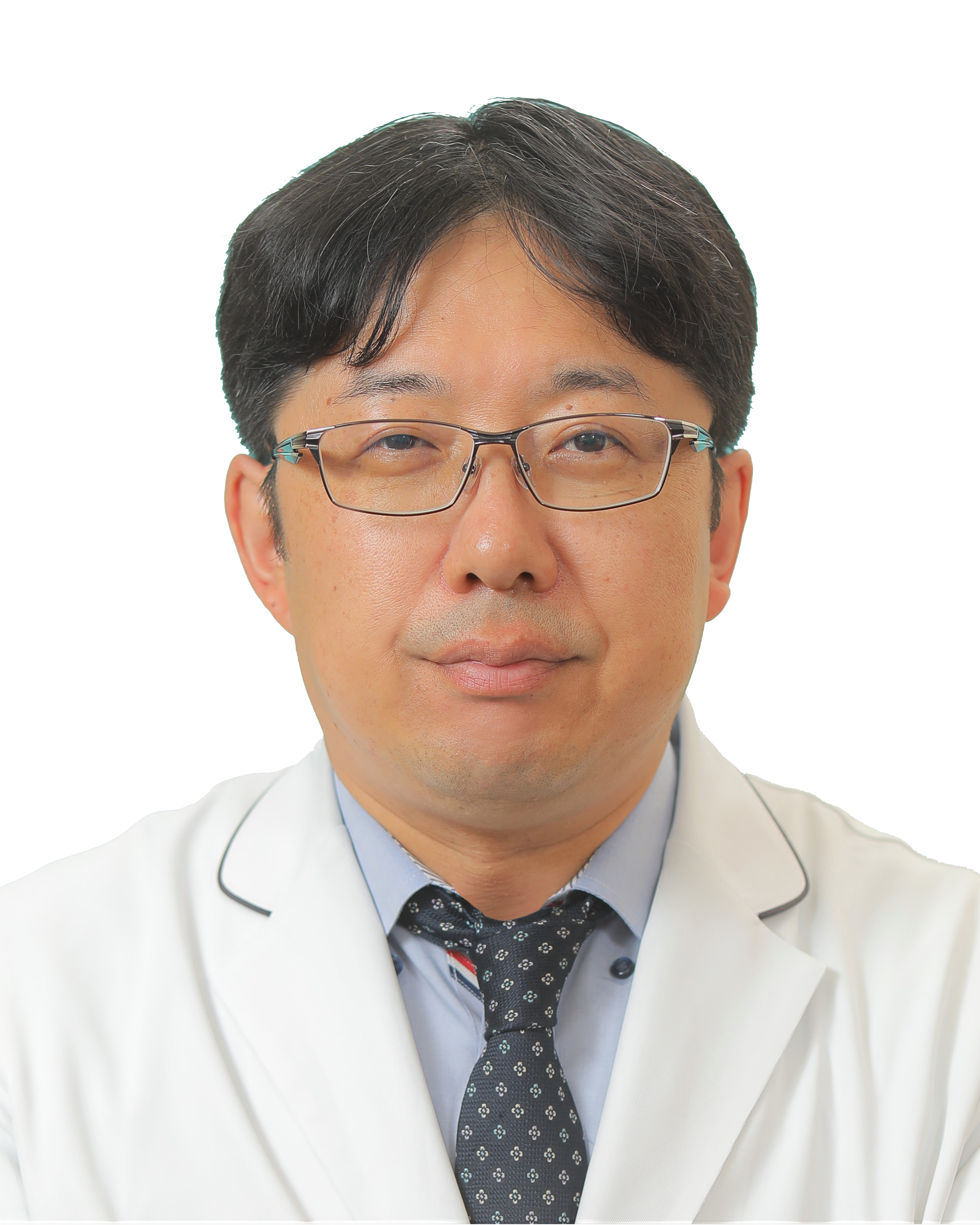
-
副部長(准教授)
清水 克彦
Katsuhiko Shimizu
専門分野
呼吸器外科(肺・縦隔)、気管支鏡治療(レーザー・ステント)、がん化学療法
認定医・専門医・指導医
日本外科学会外科専門医・指導医、日本胸部外科学会認定医・指導医、日本呼吸器外科学会指導医、呼吸器外科専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本臨床腫瘍学会指導医、日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医
- 出身大学
- 広島大学 H5.3 卒業
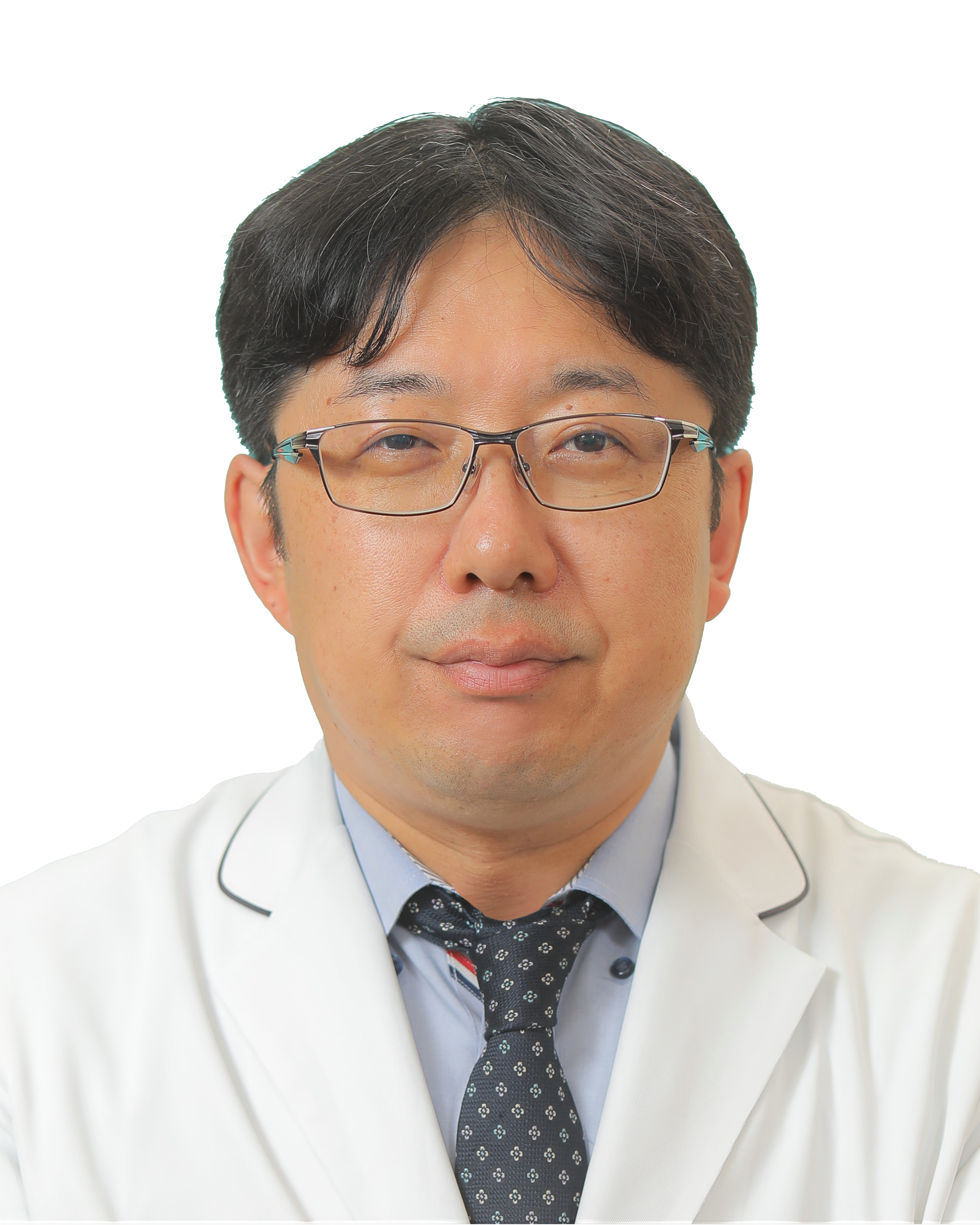
- 副部長(准教授) 清水 克彦 Katsuhiko Shimizu
専門分野
呼吸器外科(肺・縦隔)、気管支鏡治療(レーザー・ステント)、がん化学療法
認定医・専門医・指導医 日本外科学会外科専門医・指導医、日本胸部外科学会認定医・指導医、日本呼吸器外科学会指導医、呼吸器外科専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本臨床腫瘍学会指導医、日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医
- 出身大学
- 広島大学 H5.3 卒業