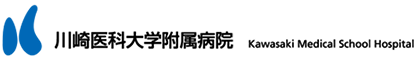肺がんとは
肺がん
人口の高齢化とともに「がん」と診断される人は年々増加しています。
最新の統計によると、日本人男性の3人に2人は一生のうち一度はがんになり、女性も2人に1人はがんと診断されます。なかでも、肺がんは大腸がん・胃がんに次いで3番目に多く、年間に12万人余りの人が肺がんと診断され増加傾向が続いています。
一方で肺がんは、大腸がんや胃がんと比べて治りにくく、肺がんを克服するためには「早期発見・早期治療」が最も重要であることに変わりはありません。
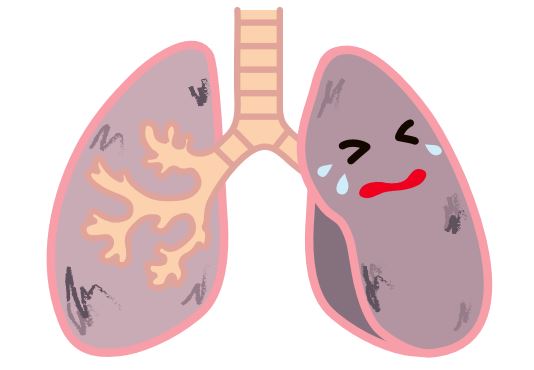
一方で腺がんは非喫煙者でも生じることがあるため、タバコを喫わないから肺がんにならないということは決してありません。

一方、腺がんや大細胞がんは肺の末梢にできやすいので、よほど大きくなるまでは症状は出てきません。肺がんが進行してくると、息切れや体重減少などの症状が現れます。

最新の統計によると、日本人男性の3人に2人は一生のうち一度はがんになり、女性も2人に1人はがんと診断されます。なかでも、肺がんは大腸がん・胃がんに次いで3番目に多く、年間に12万人余りの人が肺がんと診断され増加傾向が続いています。
一方で肺がんは、大腸がんや胃がんと比べて治りにくく、肺がんを克服するためには「早期発見・早期治療」が最も重要であることに変わりはありません。
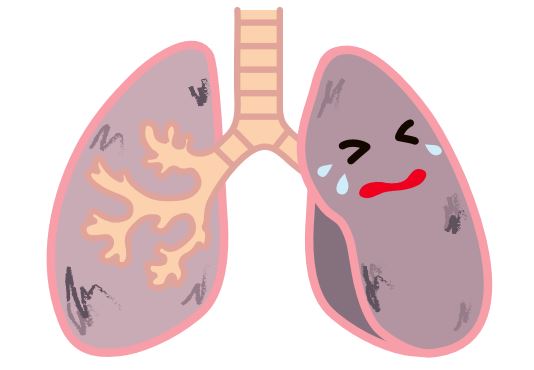
肺がんの種類
ひとくちに肺がんと言っても様々な種類(組織型)があり、多いものだけでも腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん、小細胞がんの4種類があります。小細胞がん以外の3種類の肺がんをまとめて非小細胞肺がんと呼ぶこともあります。喫煙と肺がんの関係は古くからよく知られていますが、タバコとの関連が明らかになっているのは扁平上皮がんと小細胞がんであり、喫煙率の低下とともにこれらのがんは減少傾向にあります。一方で腺がんは非喫煙者でも生じることがあるため、タバコを喫わないから肺がんにならないということは決してありません。

肺がんの症状
肺がんは組織型によって病気のできる部位が異なります。喫煙と関係がある扁平上皮がんや小細胞がんは気管に近い肺の根部にできやすく、咳・痰の増加、血痰などの症状が現れます。一方、腺がんや大細胞がんは肺の末梢にできやすいので、よほど大きくなるまでは症状は出てきません。肺がんが進行してくると、息切れや体重減少などの症状が現れます。
肺がんの検査
肺がんに特有の症状はありませんから、咳や痰の様子が変わってきた場合は早めにレントゲン検査を受けることが早期発見につながります。症状がなくても年1回程度定期的に検診を受けることも大切です。CT検査は、早期の肺がんや肺の根部にできたがんを発見するのに一層有効です。レントゲン検査で肺がんが疑われた場合、影の部分の細胞や組織を採って検査を行います。細胞を取るための方法には気管支内視鏡や経皮的針生検(局部麻酔をして身体の外から針を刺して細胞を取る検査)などがあります。採取した細胞を顕微鏡で調べて、がん細胞が発見されると肺がんの診断は確定します。がんの広がり、転移の有無を調べるためには、現在ではPET検査や脳MRI検査が行われます。これらの検査の結果で、がんのステージ(病期)が決まり、治療方針が決まっていきます。
執筆者
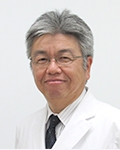
-
部長(教授)
中田 昌男
Masao Nakata
専門分野
肺がん、呼吸器外科(肺・縦隔)、胸腔鏡手術
認定医・専門医・指導医
日本外科学会認定医・外科専門医・指導医、日本胸部外科学会認定医・指導医、日本呼吸器外科学会指導医、呼吸器外科専門医
- 出身大学
- 岡山大学 S60.3 卒業
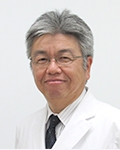
- 部長(教授) 中田 昌男 Masao Nakata
専門分野
肺がん、呼吸器外科(肺・縦隔)、胸腔鏡手術
認定医・専門医・指導医 日本外科学会認定医・外科専門医・指導医、日本胸部外科学会認定医・指導医、日本呼吸器外科学会指導医、呼吸器外科専門医
- 出身大学
- 岡山大学 S60.3 卒業