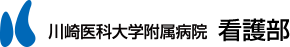チーム医療の実践

チーム医療
1人の患者さんの症状や状態に合わせ、
さまざまな分野の医療スペシャリストが連携して
治療やサポートに当たります。
医療安全管理室
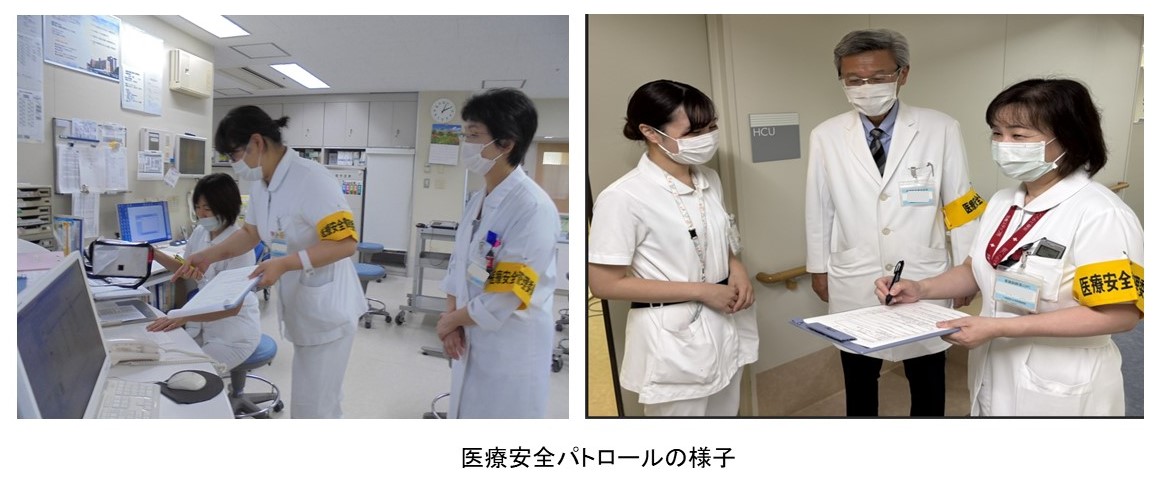
感染管理室
感染管理室では、臨床現場の職員が感染対策を実践できるように、耐性菌の分離状況、抗菌薬の使用状況などの情報について確認する院内感染制御チーム(ICT)、各部署の感染対策や環境についてチェックを行う院内環境感染制御スタッフ(ICS)を設置し、いずれも医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員など多職種・多部門のメンバーで構成され、組織横断的に活動しています。毎週、病棟と外来・検査部門をラウンドし、現場のスタッフから感染対策の相談を受けることもあり、院内感染対策の実践につなげています。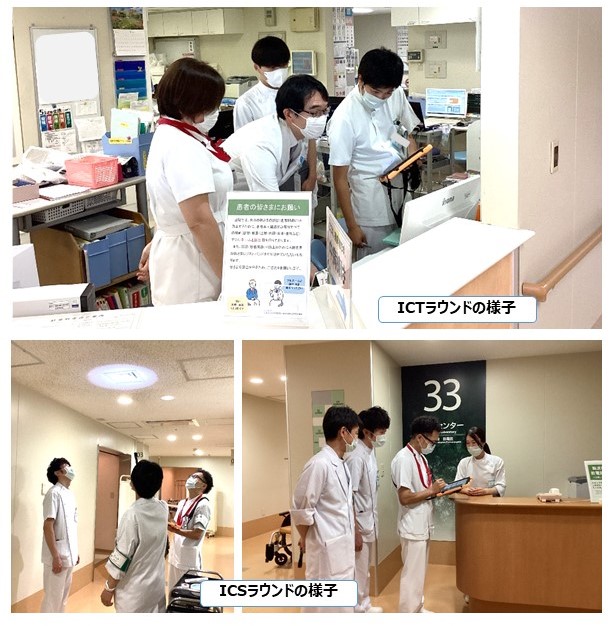
ベッドコントロールセンター
当センターでは、患者さんが安心して治療や療養を受けられるよう、入院受け入れから退院までの調整を行っています。適切な療養環境の確保と円滑な病床運用を通じて、質の高い医療の提供を支えています。
退院支援では、多職種が連携して情報を共有し、患者さん一人ひとりに合わせた支援を行っています。住み慣れた地域でその人らしく生活を続けられるよう、地域とのつながりを大切にし、心の通った支援を目指しています。
また、各病棟にはリガールナース(部署退院支援看護師)を配置し、ベッドコントロールセンターと連携しながら、多職種による協働体制で支援を行っています。
褥瘡対策室
当院は、重症患者さんが多く入院されるため、褥瘡が発生しやすい状況にあります。そこで、褥瘡予防、褥瘡の早期発見・早期治癒をめざして褥瘡対策室が中心的役割として活動しています。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの多職種が協働し、入院患者さん一人ひとりについて褥瘡対策を検討し、適切なケア・治療が行えるよう働きかけています。褥瘡回診では形成外科・美容外科医師や管理栄養士と褥瘡管理者(皮膚・排泄ケア認定看護師)が、定期的に褥瘡の評価を行い、褥瘡の病態に応じたケアの提供を行えるように努めています。
カンファレンスの様子
緩和ケアチーム
当院の緩和ケアチーム「カワサキ」は、がん患者さんとそのご家族の苦痛を軽減し、より良い療養生活を送っていただけるよう、多職種によるチーム医療を行っています。
チームには、身体症状・精神症状の担当医師をはじめ、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、リハビリ専門職など、さまざまな分野の専門スタッフが参加しています。
毎週木曜日に行うカンファレンスでは、病棟スタッフやホリスティックナース(リンクナース)、主治医と情報を共有し、病棟ラウンドを通して患者さん一人ひとりに合ったケアの方針を検討・提案しています。
また、2か月に1回のペースで第1木曜日には、緩和ケアに関心のあるホリスティックナースを対象とした勉強会を開催しており、日々の実践を振り返りながら、ケアの質の向上に努めています。
緩和ケアチームでは、がん患者さんとその家族を「一人の人」として全人的に捉え、身体的・精神的・社会的・スピリチュアルな側面から多角的に支援を行っています。苦痛の緩和だけでなく、生活の質(QOL)の維持・向上を目指し、寄り添う医療を提供しています。
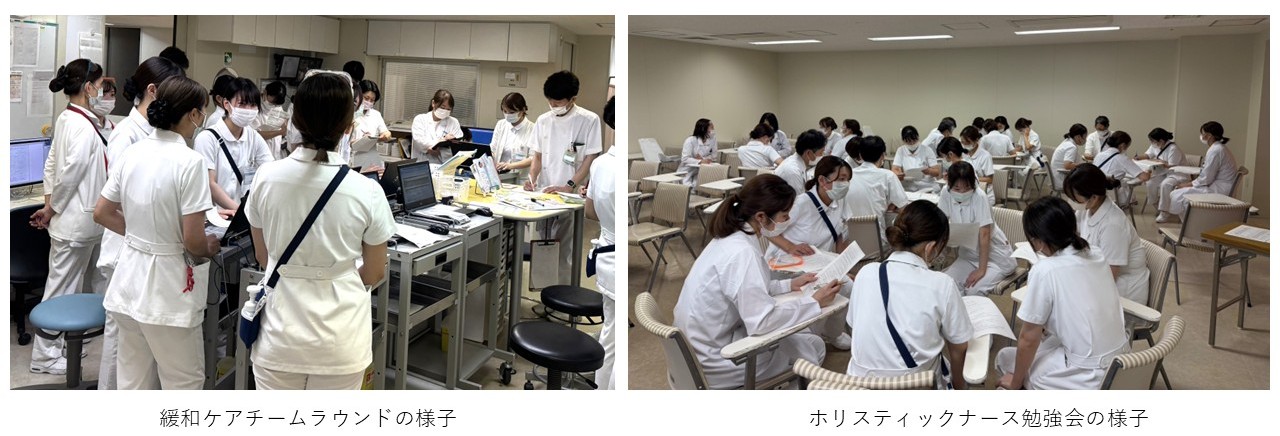
栄養サポートチーム(NST)
栄養サポートの始まりは、入院時のときに全患者さんに行う栄養評価からです。必要によりNSTチームへサポート依頼をします。
サポート患者さんに対しては、毎週火曜日のカンファレンスで、栄養サポートの方針を決めます。その後、医師と看護師、薬剤師、管理栄養士との4職種でラウンドを行い、患者さんの要望を取り入れ、担当者と今後の方針を話し合います。
また、当院では、NST専門療法士研修があり、NSTへの普及活動をしています。
NSTカンファレンスの様子